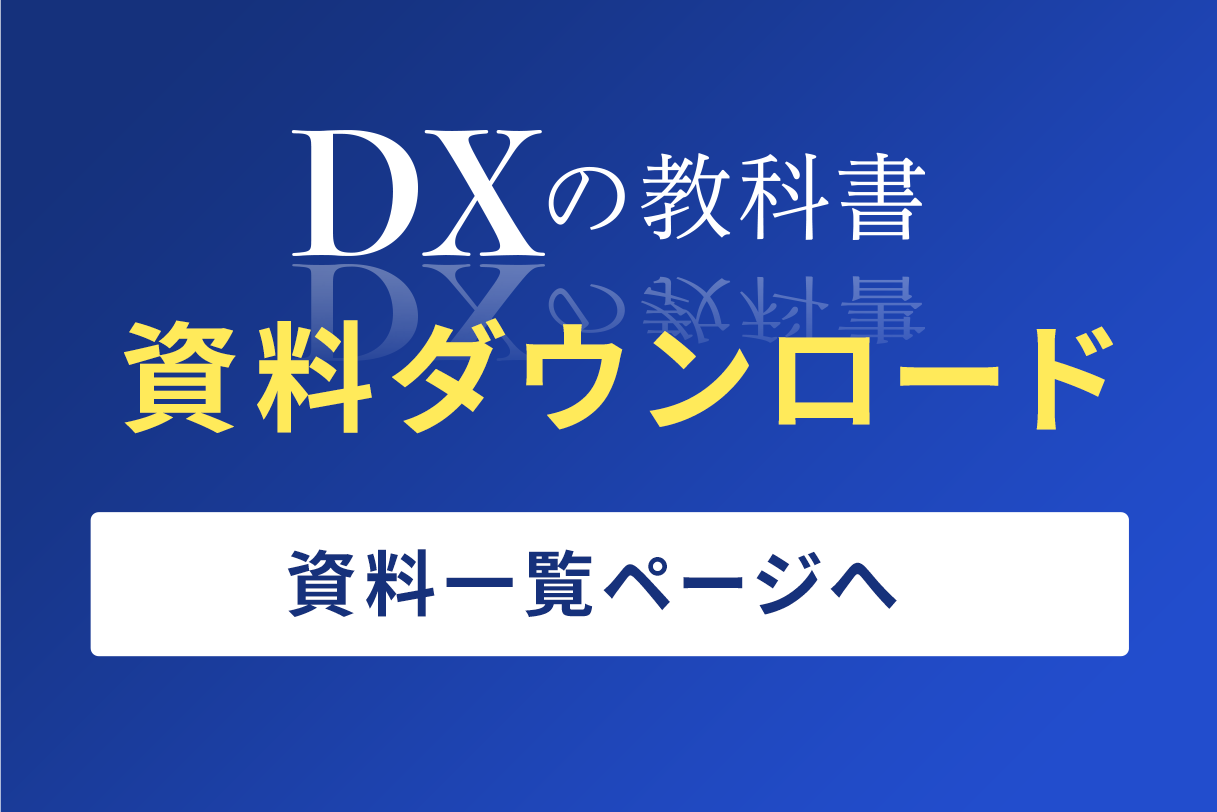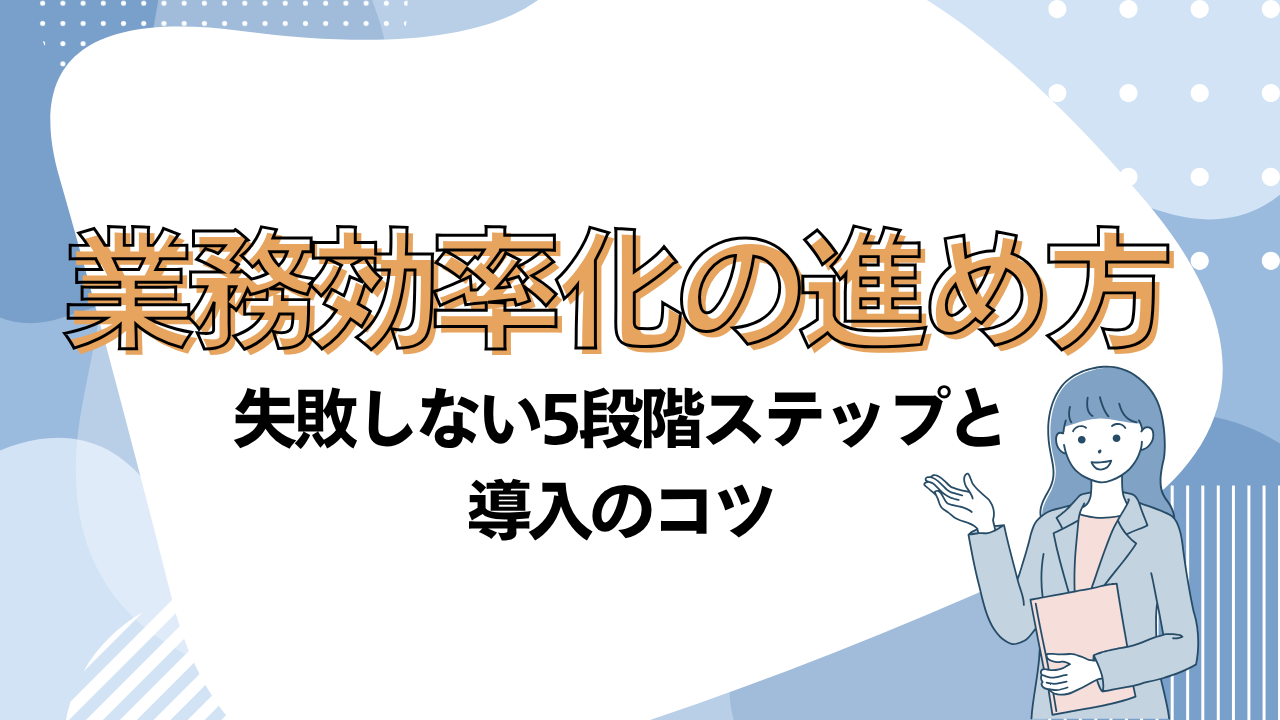「業務効率化に取り組みたいが、何から着手すべきか分からない」そんな悩みを抱える担当者に向けて、この記事を書いています。効率化を成功させるポイントは、最初からすべてを変えようとしないこと。まずは小さく始め、効果を検証しながら仕組みを整えていく。 その積み重ねが、長期的な改善につながります。
本記事では、業務効率化をスムーズに進めるための5つのステップを紹介します。 「何から始めればよいか整理したい」「現場で実際に回る仕組みを作りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
業務効率化とは?なぜ今、必要なのか

業務効率化とは、単に作業スピードを上げることではなく、限られた人員や時間の中で生産性を高める“仕組みづくり”です。では、なぜ今あらためて業務効率化が求められているのでしょうか。その背景を整理してみましょう
人手不足・コスト削減のプレッシャーを改善
「人が足りない」「採用しても定着しない」「結局、同じメンバーで回すしかない」。
こうした声が、いま多くの企業で聞かれるようになりました。
人手不足やコスト削減のプレッシャーが高まるなか、 限られたリソースで成果を上げるために注目されているのが、ツールを活用した業務効率化です。
単純作業や繰り返し業務をツールに任せ、人がより創造的な仕事に集中できる環境を整える。 この発想の転換こそが、今あらためて求められている業務効率化の本質です。
属人化のリスクを回避し、働き方改革を進める
以前から課題とされてきた「属人化」は、リモートワークの定着により、さらに顕在化しました。 「この作業はあの人しかできない」という状況は、組織全体のリスクにつながります。
誰が担当しても同じ品質で進められる仕組みをつくるためには、 マニュアル整備や手順の明確化、自動化ツールの導入が欠かせません。
“人が変わっても進む仕組み”を整えること。 それが業務の安定と安心を生み、働く人が力を発揮できる環境につながります。 業務効率化とは、現場が健やかに成果を出せる“組織づくりの戦略”です。
【関連記事】
中小企業の業務効率化とは?自動化で実現する仕組みづくりの進め方と効果を解説
業務効率化の進め方|失敗しない5段階ステップ
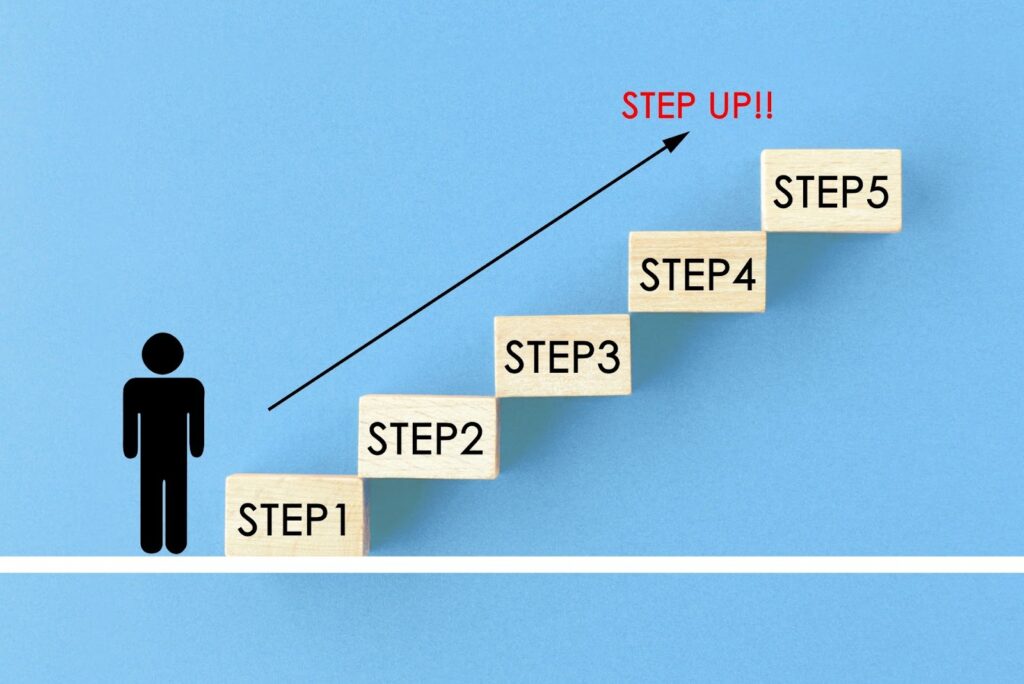
ここからは、「何から始めればいいのか分からない」という方に向けて、 業務効率化をスムーズに進めるための基本ステップを5段階で紹介します。
ポイントは、いきなり完璧を目指さず、“小さく始めて成果を出す”こと。 このステップを理解すれば、どんな現場でも無理なく効率化を進めるための「全体像」が見えてきます。
ステップ1:業務を洗い出す
業務効率化の出発点は、現状を正確に把握することです。まずは、どんな業務がどのくらい発生しているのかを可視化します。Excelへの転記、請求書処理、メールの定型送信など、日々時間を取られている業務を具体的に書き出すことが第一歩です。
チーム全体で意見を出し合い、担当者ごとの作業を見える化すると、「意外と手作業が多い」「同じ作業を複数人が行っていた」などの非効率の要因が見えてきます。
この段階では、改善よりも“現状の棚卸し”に集中します。事実を洗い出すことで、後の優先順位付けや手法の選定がスムーズになります。
ステップ2:優先順位を決める
すべての業務を一度に改善しようとすると、途中で手が止まってしまいます。 まずは、効果が大きく、すぐに着手できる業務から取り組みます。件数が多い入力作業や、定期的に繰り返されるタスクなど、改善効果の高い業務を選ぶことがポイントです。
「効果が高い」とは、時間削減・コスト削減・ミス防止・属人化解消など、 何を成果とするかによって変わるという点を意識しておきましょう。自社にとって“最も改善すべき効果”を整理すれば、限られたリソースでも効率的に進められます。
下の整理表を参考に、まずは業務を洗い出してください。改善の優先度が見えてきたら、次は“どの方法で改善するか”を検討する段階です。
業務効率化における「効果の観点」整理表
| 効果の種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 時間削減効果が高い | 作業時間を大幅に短縮できる業務 | データ入力、請求書作成、レポート作成など |
| コストカット効果が高い | 人件費や外注費を減らせる業務 | 紙の処理・郵送対応、手動の見積作成など |
| ミス削減効果が高い | ヒューマンエラーを防げる業務 | 数値転記、メール送信、顧客データ管理など |
| 属人化解消効果が高い | 特定の人しかできない業務を仕組み化できる | 独自Excel管理、担当者依存の報告書作成など |
| 生産性向上効果が高い | 本来の業務(提案・分析・企画)に時間を使える | 営業資料作成、会議資料の自動更新など |
ステップ3:業務効率化の方法を選ぶ
改善対象が決まったら、どの方法で効率化するかを検討します。 重要なのは、「自社でできること」と「外部に任せること」を見極めることです。
まずは、代表的な業務効率化の手法を整理しましょう。 それぞれの特徴を理解すると、どんな業務にどの方法が向いているかが見えてきます。
業務効率化を実現する代表的な5つの手法
| 手法 | 特徴 | 向いている業務 |
|---|---|---|
| RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) | 定型業務の自動化に最適。人の操作をそのまま再現できる | データ転記、帳票出力、請求処理など |
| ノーコードツール | 専門知識がなくても自分で簡単に仕組みを構築できる | フォーム入力、タスク管理、通知連携など |
| プログラミング | 自社特有の業務フローに合わせて、オーダーメイドで開発できる | 受注〜決済、基幹システム、社内ツールの連携など |
| クラウドサービス | サーバーやインフラを持たずに利用できる。導入・運用が手軽 | 顧客管理、営業支援、会計処理、勤怠管理など(サービスによって異なる) |
| 外注 | 専門知識や工数が必要な業務をプロに任せられる | システム開発、大規模連携、自動化の全体設計など |
どの方法を選ぶか迷ったときの「3つの視点」
業務効率化の代表的な手法を理解したら、次に自社に合った方法を選ぶ段階です。迷ったときは、次の3つの視点を基準に考えると整理しやすくなります。
① 業務効率化の目的(何を改善したいのか)
時間・コスト・ミス削減など、改善の目的によって最適な手法は異なります。まずは「何を最優先で改善したいのか」を明確にします。
② リソース(社内で対応できる範囲)
次に、導入後の運用を継続できる体制があるかを確認します。ノーコードツールを扱える人材や、運用を担う担当者を確保できるかを整理しておきましょう。こうした観点を明確にすることで、「自社で進める部分」と「外部に任せる部分」の線引きが見えてきます。
③ 制約条件(費用・期間・セキュリティ)
最後に整理したいのが、「どこまでの範囲で実現できるか」という現実的な条件です。
予算や期間、セキュリティの観点を先に明確にすることで、 上司への提案や稟議もスムーズに進みます。たとえば、以下のようなポイントを確認しておきましょう。
ツール選定・導入前に整理しておきたいポイント
| 項目 | チェックポイント | 具体例・補足 |
|---|---|---|
| 費用面 | 導入にかけられる上限は? | サブスク型 or 買い切り型/ランニングコストの有無 |
| 期間 | いつまでに成果を出す必要があるか? | 四半期・年度内・プロジェクト期間など |
| セキュリティ | 個人情報・顧客データを扱う業務でも安全か? | 社外アクセス制限、ログ管理、クラウドの安全性 |
| 運用体制 | 導入後、誰が保守・運用を担当するか? | 担当者の兼任・外部委託・ツールベンダーのサポート有無 |
| スケール(拡張性) | 他部署への展開がしやすいか? | 横展開のしやすさ、API連携の有無 |
| サポート体制 | 導入時やトラブル時の支援は受けられるか? | 無料相談・サポート窓口・トレーニング有無 |
ステップ4:小さく試す
改善の方向性が見えてきたら、いきなり全社導入せず、小さく試す段階へ進みます。 一部門・一業務から始めることで、想定外の課題や改善点を早期に把握できます。たとえば「経理部の請求書処理だけ」「営業部の定期メール送信だけ」といった、 限られた範囲で試すことで、失敗リスクを抑えながら確実に前進できます。
導入後は、現場担当者の声を集め、操作性・工数・連携面などを確認します。 フィードバックをもとに設定や運用ルールを微調整し、実運用に耐えられる仕組みを整えていきます。
ステップ5:効果を測定し、横展開する
最後に、導入効果を数字で見える化します。 削減できた時間・工数・ミス件数などを具体的に示すことで、 上司や他部署に共有しやすくなり、社内全体の理解も得られます。
成果が出たら、その仕組みを他部署にも展開していきましょう。 同じ方法を繰り返すことで、業務効率化の文化が社内に根づくようになります。
業務効率化は一度きりの施策ではなく、組織を成長させる仕組みづくりです。 ここまでのステップで得た知見を活かし、持続的に改善を進める体制を整えていきます。こうして“業務効率化の文化”が少しずつ社内に根づくことで、継続的な改善へとつながります。
業務効率化は、内製か外注か?判断のポイント
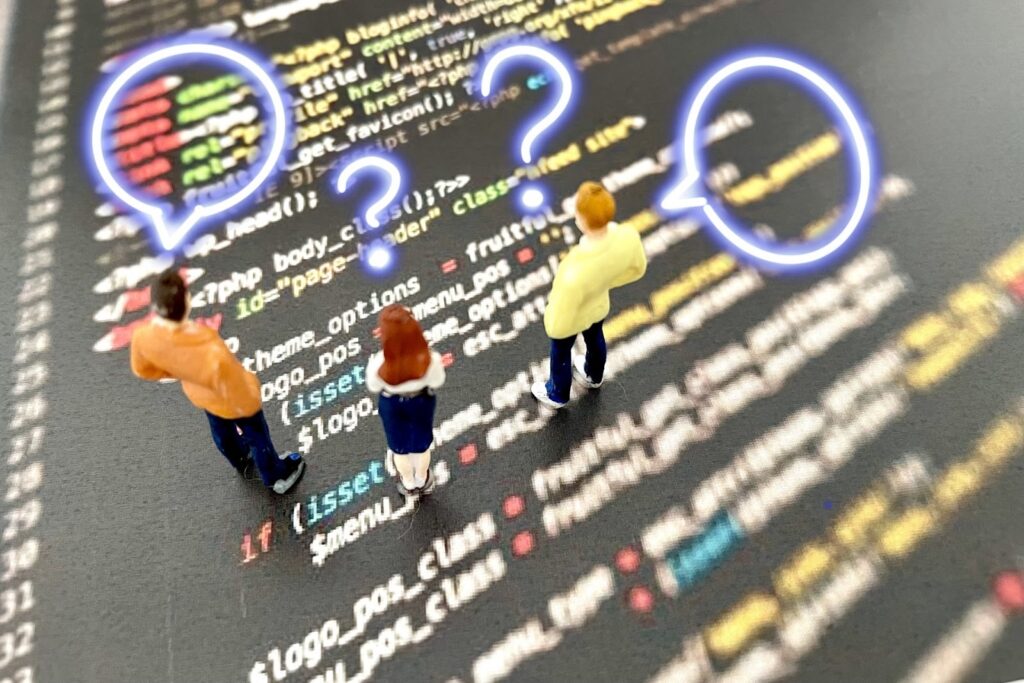
業務効率化の方向性が見えてきたら、次に考えたいのが「自社で進めるべきか、それとも外部に任せるべきか」という判断です。
どちらにもメリットとデメリットがあり、 社内のリソースやスピード感、求める成果によって最適な選択は異なります。 ここでは、それぞれの特徴と判断の目安を整理します。
内製のメリット(ノウハウ蓄積・スピード感)
内製化の最大のメリットは、自社の中にノウハウを蓄積できることです。 仕組みを理解して運用できるようになれば、 改善やカスタマイズをスピーディに進めることができます。
また、現場の課題をその場で反映できる柔軟さも魅力です。 小さく始めて、自社のペースで成長させたい企業には特に向いています。
外注のメリット(専門知識・安定運用)
一方で、外注の強みは専門知識と安定した運用です。 RPAやAPI連携など専門スキルを要する領域は、 最初から外部のプロに任せたほうがスムーズに進むケースも多くあります。
また、担当者の異動や退職などに左右されず、 長期的に安定した仕組みを維持できるのも外注ならではの利点です。
併用パターン(まずは外注、小さく内製へ)
最近では、「外注+内製」のハイブリッド型を選ぶ企業が増えています。 初期構築や設計は外部に任せ、運用や改善は社内で行うスタイルです。こうすることで、短期間で成果を出しながら、 徐々に社内に知見をためて“自走できる体制”へと移行できます。
💡もし迷ったら、無料で相談できます
ここまで整理してみて、「判断が難しい」と感じる場合は、第三者の視点を取り入れるのも一つの方法です。ジドウカでは、経験豊富なスタッフが現状の整理から最適な進め方までサポートしています。まずは気軽に、無料相談をご活用ください。
【関連記事】
中小企業の業務効率化は本当に効果がある?自動化で実現する仕組みづくりと改善事例
業務効率化を成功させる社内体制と推進役の作り方

業務効率化を進めるうえで、担当者ひとりの努力だけでは限界があります。ツールを導入しても、現場の理解や協力が得られなければ定着しません。ここでは、効率化を“組織として継続させるための体制づくり”のポイントを紹介します。
業務効率化、推進リーダーの役割
業務効率化の中心となるのが、推進リーダーです。 ツール導入だけでなく、目的を共有し、経営層や現場との橋渡し役を担います。
推進リーダーが意識したいポイントは次の3つです。
- 目的を明確に伝える(なぜ効率化が必要かを共有)
- 現場の課題をヒアリングする
- 導入後もフォローし、改善を重ねる
業務効率化を進めるには、経営層のコミットメントは必須
業務効率化を社内で進めるには、経営層の理解と支援が欠かせません。 経営層が“全社的な取り組み”としてメッセージを発信することで、社内の意識が統一されます。 小さな成功を積み上げて成果を可視化し、定期的に経営層へ報告する仕組みをつくると効果的です。
なぜ経営層のコミットメントが必要なのか
- 意思決定のスピードが上がる(予算・リソース・優先順位の判断が早くなる)
- 社内全体への影響力がある(現場が「会社方針」として受け止めやすい)
- 継続的な取り組みにできる(人事異動や組織変更があっても軸がぶれない)
- 成功事例の発信で社内が動く(経営層が成果を共有することで他部署が協力しやすくなる)
業務効率化に現場スタッフを巻き込む方法
業務効率化が停滞する原因のひとつに、「現場の抵抗感」があります。「これまでのやり方を変えたくない」「新しいツールは難しそう」と感じる人は少なくありません。せっかく導入しても、現場が使いこなせず“形だけの改善”に終わるケースもあります。
だからこそ、導入前から現場の声を聞き、「なぜこの取り組みが必要なのか」「どんな効果があるのか」を丁寧に共有することが大切です。
現場を巻き込むための工夫例
- 導入前に現場の課題をヒアリングする
- 操作テストに現場メンバーを参加させる
- 改善提案を歓迎する雰囲気をつくる
こうした取り組みを重ねることで、現場が“当事者”として関わるようになります。一人の担当者が推進するのではなく、チーム全体で仕組みを育てていく姿勢が大切です。
💡ポイント
業務効率化は「仕組みを導入して終わり」では意味がありません。 リーダーの旗振り+経営層の支援+現場の納得の3要素がそろって、初めて定着します。社内の一体感を生みながら改善を継続することで、 “効率化が文化として根づく組織”へと進化していきます。
【関連記事】
業務効率化はなぜ定着しない?自動化ツール運用で差がつく“続ける仕組み”とは
やってはいけない業務効率化の失敗例

業務効率化は、多くの企業で注目されているテーマですが、 実際には「導入したのに効果が出ない」「結局続かなかった」という声も少なくありません。ここでは、よくある3つの失敗パターンと、その回避策を紹介します。
失敗①:全部一気にやろうとして失敗する
最初からすべての業務を自動化しようとすると、 ツールの選定や運用ルールが追いつかず、現場が混乱しがちです。
まずは「定型的で効果の出やすい業務」から小さく始め、 成果を出してから徐々に広げるのが成功の鉄則です。
失敗②:現場を巻き込まずに進めて失敗する
私の経験でも、経営層や担当者だけで決めてしまうと、 実際にツールを使う現場がついてこられず、定着しないケースが多く見られます。
導入前に現場の声をヒアリングし、 「どんな点が不便か」「何を改善したいか」を共有することで、スムーズな浸透につながります。
失敗③:導入後の運用を軽視して失敗する
導入がゴールになってしまい、 その後の改善や運用ルールづくりが追いつかないケースも少なくありません。
効率化の仕組みは“一度作って終わり”ではなく、 業務の変化に合わせてアップデートしていくことが大切です。
💡失敗を防ぐ3つの心得
- 小さく始めて成果を可視化する
- 現場の声を最初から取り入れる
- 導入後も継続的に改善する
この3つを意識するだけで、 「導入して終わり」ではなく、「成果が定着する効率化」へとつながります。
無料から始められる業務効率化の方法

ここまでで業務効率化の進め方や体制の作り方を整理してきました。 次のステップでは、「まずは小さく試してみる」ことへ進みましょう。
いきなり大規模に導入するより、 無料で試しながら自社に合った方法を探る方が、リスクも少なく成果も出やすいです。 ここでは、導入ハードルを下げて始められる3つの方法を紹介します。
無料で試せるツール例(Zapier・Googleスプレッドシート連携など)
まずは、無料プランのあるツールを活用して“自動化の感覚”をつかんでみましょう。
おすすめツールその①:Zapier(ザピア)

アプリ間のデータ連携を自動化できるツール。
例)フォーム送信 → スプレッドシートに自動記録 → Slackに通知
おすすめツールその②:Googleスプレッドシート × Google Apps Script

GoogleスプレットシートやGoogleドキュメントなどGoogleツールを使っているのであれば、社内にあるデータ整理や集計作業を自動化することが可能。コード不要で簡単に実装できます。Googleアカウントさえあれば利用でき、無料で試せる範囲も広いのが魅力です。
例)定期レポートの自動作成、データ集計やメール送信の自動化など
【Google App Scriptを使った詳しい自動化の例】
Gmail受信をトリガーにスプレッドシートを自動で複製する方法3選
おすすめツールその③:Sikulix(シクリ / シクリックス)
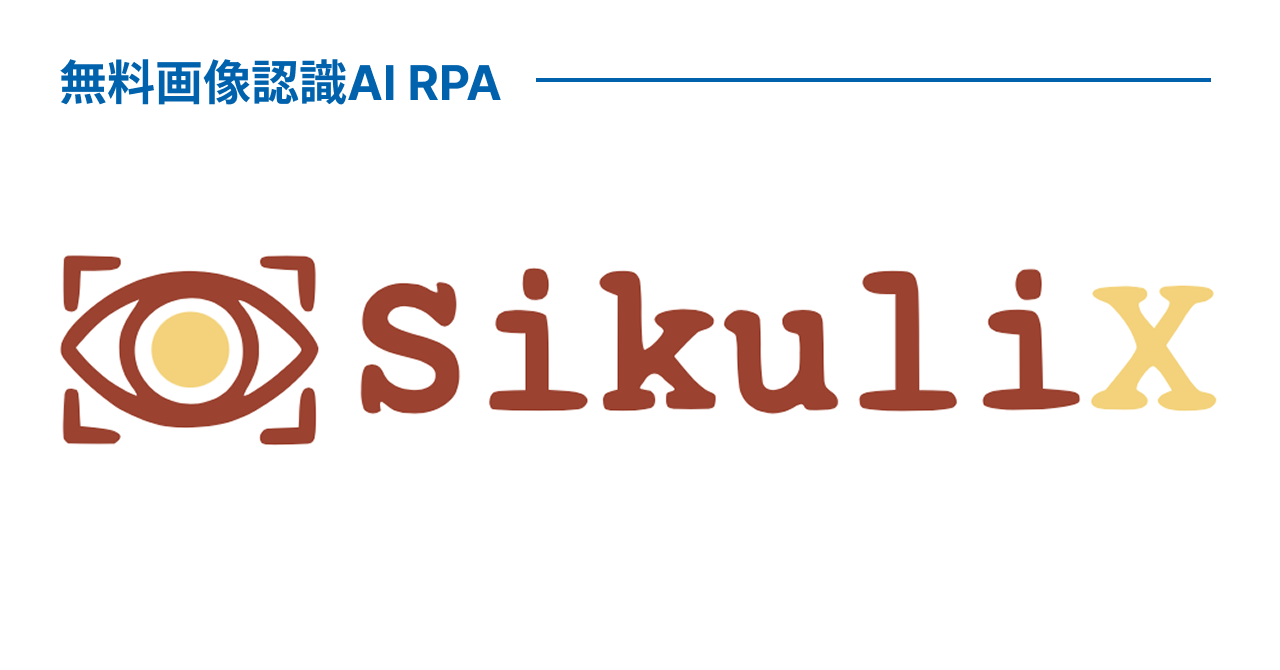
日常的な定型的な業務を安定的に毎日同時刻に決めた通りに稼働させることができるツール。毎日、「決められたことを決められた時間に決めたられたルールに従って行う」ような社内業務と相性が良いのが特徴です。
例)基幹システムやWebアプリケーションから日次売上データを夜中に自動抽出など
社内で小規模にPoC(概念実証)をする
新しいツールを導入する際は、PoC(Proof of Concept:概念実証として小規模に試してみるのがおすすめです。PoCとは、「この仕組みが本当に効果を発揮するか?」を確認するためのテスト導入のこと。失敗してもリスクが小さく、現場の反応や運用上の課題を早い段階で発見できます。
たとえば、次のような「小さな成功」を積み重ねる形がおすすめです。
✅経理部で「請求書処理だけ」を自動化してみる
✅営業部で「定期メール送信だけ」を自動化してみる
✅管理部で「社内申請フローだけ」をノーコード化してみる
こうして部分的に導入することで、「どの業務に一番効果があるか」を見極めながら、社内の理解と協力を得やすくなります。
無料お試しサービスを活用する
自社でツールを探す時間がない場合は、 業務自動化の専門サービスの無料相談やトライアルを利用するのがおすすめです。
課題の整理から、自社に合うツール選定まで一緒に考えてもらえるため、 「どこから始めればいいかわからない」という段階でもスムーズに進められます。
ジドウカでも、無料で業務内容の棚卸しと自動化プランの提案を行っています。
👉 ジドウカ 無料相談フォーム
業務効率化を“失敗しない”ためのジドウカ実践事例
業務効率化の本質は、現場で成果が出る仕組みをつくることにあります。 ここでは、ジドウカで支援した企業の中から、属人化を解消し、データドリブン経営を実現した事例を紹介します。課題の整理から定着までのプロセスを通じて、成果につながる改善の進め方を見ていきましょう。
🏢 導入企業:ベジクル株式会社(東京都)

事業内容: 業務用野菜の卸事業を展開し、1日約1,000店舗以上へ配送。 データ管理と情報共有の非効率が、事業拡大のボトルネックとなっていました。
課題
・システムが外部連携に対応しておらず、データ抽出〜共有を手作業で対応しており面倒だった。
・担当者ごとに運用方法が異なり、KPIの管理や離反率の把握が属人的になっていた。
改善アプローチ
・RPA+Google Apps Scriptを組み合わせ、データ抽出〜Slack通知までを自動化。
・売上・客単価・離反率などをリアルタイムで可視化し、現場と経営が同じ情報を共有できる仕組みを構築。
・システム連携・通知設計・運用ルールまでを一貫して整備し、再現性のある運用体制を確立。
効果
・KPIの見える化と離反管理を効率化し、現場担当者の業務負担を大幅に削減。
・手作業中心だったオペレーションを刷新し、「勘と経験」から「データに基づく判断」へシフト。
・部署間の連携がスムーズになり、改善サイクルが継続的に回るように。
【元記事】
データドリブン経営の思想基盤を自動化で実現。半同期的な「データ解析・共有」により事業の解像度を上げ、よりシャープな意思決定に活用。
まとめ|“導入で終わらせない”業務効率化が、成果を生む
業務効率化は、ツールを導入することがゴールではありません。 現場で実際に成果を出し、その仕組みを組織に根づかせることこそが、本当の効率化です。
重要なのは、最初から完璧を目指すことではなく、小さく試して改善を重ねること。 一つずつ成功体験を積み上げることで、チーム全体の意識と生産性が確実に変わっていきます。
この記事で紹介した5つのステップを参考に、 「どの業務を効率化すべきか」「どんな方法が自社に合っているか」を整理してください。 上司やチームに“説明できる状態”をつくることが、すでに実践の第一歩です。
💡 まずは無料から始める“仕組みづくり”
「自社の業務でも効率化できるか知りたい」
「どのツールを選べばいいか相談したい」
そんな方は、ジドウカの無料相談をご活用ください。 経験豊富なスタッフが、現場の課題整理から最適な改善プランの設計まで、貴社に合わせて伴走支援します。